「死にゲーに興味があるけれど、難しそうで手が出せない…」 「エルデンリングが話題だけど、初心者の自分でも楽しめるのかな?」 「何度も死んでイライラするだけのゲームなんて、本当に面白いの?」
このような不安を抱えている死にゲー初心者の皆さん、その気持ちとてもよく分かります。筆者も最初は「こんな理不尽なゲーム、絶対に無理」と思っていた一人でした。
しかし実際にプレイしてみると、死にゲーには他のジャンルでは絶対に味わえない特別な魅力があることを発見したのです。「また死んでしまった…でも今度こそクリアできそう!」という、負けるたびに燃え上がる不思議な中毒性。そして困難を乗り越えた時の、言葉では表現できないほどの達成感。
でも、どの作品から始めればいいか分からないというのが、多くの初心者が抱える共通の悩みでしょう。間違った作品を選んでしまうと、死にゲーの本当の面白さを知る前に挫折してしまうリスクもあります。
そこで本記事では、50本以上の死にゲーをプレイしてきた経験を基に、初心者でも安心して楽しめる7作品を厳選してご紹介いたします。
「死にゲーを始めてみたいけど不安」という方も、この記事を読み終える頃には「これなら自分でもできそう!」と思えるはずです。ぜひ最後までお付き合いください。
死にゲー初心者におすすめの入門作品7選
死にゲー初心者におすすめしたい入門作品を、難易度順に7つご紹介します。それぞれの作品には異なる魅力があるため、ご自身の好みに合わせて選んでいただけるでしょう。
エルデンリングは死にゲー初心者に最適な理由
エルデンリングは、2022年に発売されたフロム・ソフトウェアの最新作で、間違いなく死にゲー初心者に最も適した作品と言えます。従来の死にゲーが持つ高難易度はそのままに、初心者でも楽しめる革新的な仕組みが数多く取り入れられているからです。
実際に筆者の友人も「死にゲーは絶対に無理」と言っていたにも関わらず、エルデンリングでは100時間以上プレイしてクリアを達成しました。その理由を詳しく見ていきましょう。
オープンワールド設計で挫折しにくい
エルデンリングの最大の特徴は、オープンワールド設計による自由度の高さにあります。従来の死にゲーでは、強敵に阻まれると他に行く場所がなく、そこで詰んでしまうケースが多々ありました。
しかしエルデンリングなら、難しいボスがいても別の場所を探索して経験値を稼いだり、より良い武器を見つけたりできるのです。例えば、序盤の「マルギット」というボスで苦戦している場合でも、南の半島を探索してレベルを上げれば、格段に戦いやすくなります。
この仕組みにより、「進めなくて諦める」という状況がほとんど発生しません。常に別の選択肢があるため、初心者でも自分のペースでゲームを楽しめるでしょう。
遺灰システムで協力プレイ可能
遺灰システムは、エルデンリングが初心者に優しい理由の一つです。これは、戦闘中にAIの仲間を召喚できる機能で、実質的に2対1や3対1の状況を作り出せます。
特に「腐敗した血の狩人、フィンレイ」や「模倣者の雫涙」といった強力な遺灰を使えば、難しいボス戦も大幅に楽になるのです。筆者が初めてプレイした際も、この遺灰システムのおかげで多くの難所を乗り越えられました。
重要なのは、これが「救済措置」ではなく「正式なゲーム機能」として設計されている点でしょう。使うことに罪悪感を感じる必要は全くありません。
レベル上げによる救済措置が充実
エルデンリングでは、レベル上げによる成長要素が非常に充実しています。ステータスを上げることで、攻撃力や体力、魔力など様々な能力を向上させられるため、プレイヤーのスキルだけでなく「キャラクターの強さ」でも困難を乗り越えられるのです。
実際に、レベル50とレベル80では体感できるほど戦闘の難易度が変わります。「どうしても倒せない敵がいる」という場合でも、少しレベルを上げるだけで意外とあっさり勝てることが多いでしょう。
ダークソウル3が初心者向けの入門作品
ダークソウル3は、死にゲーの王道を学びたい死にゲー初心者に最適な入門作品です。シリーズの集大成として作られただけあって、過去作の良い部分を取り入れつつ、理不尽な要素を排除した絶妙なバランスを実現しています。
多くの死にゲー愛好者が「最初にプレイするならダークソウル3」と推薦するのも、この完成度の高さが理由でしょう。
シリーズ最高のゲームバランス
ダークソウル3は、シリーズ最高のゲームバランスを誇ります。敵の攻撃パターンは複雑でありながらも理解可能で、プレイヤーが学習して上達していく過程が非常に気持ち良く設計されているのです。
例えば、序盤のボス「グンダ」は、初見では強敵に感じるものの、何度か挑戦すると攻撃のタイミングや回避方法が分かってきます。この「最初は無理だと思ったけれど、慣れると倒せるようになる」という体験こそが、死にゲーの醍醐味と言えるでしょう。
理不尽な即死攻撃や、対処不可能な敵配置がほとんどないため、負けたときも「自分のミス」だと納得できる場面が多いはずです。
豊富な武器種で戦闘スタイル選択可能
ダークソウル3では、豊富な武器種が用意されており、プレイヤーの好みに応じて様々な戦闘スタイルを選択できます。剣と盾を使った堅実な戦い方から、大剣での豪快な攻撃、魔法を駆使した遠距離戦まで、選択肢は実に多彩です。
筆者の経験では、最初は「騎士」の職業で直剣と盾を使った戦い方から始めることをお勧めします。この組み合わせは最も安定しており、死にゲーの基本である「敵の攻撃を防ぐ→反撃する」という流れを自然に学べるからです。
慣れてきたら、より攻撃的な武器や魔法にも挑戦してみると良いでしょう。
オンライン協力プレイで助け合える
ダークソウル3のオンライン協力プレイ機能は、初心者にとって心強い味方となります。他のプレイヤーを呼んで一緒にボス戦に挑んだり、逆に困っている人を助けに行ったりできるのです。
特に難しいボス戦では、経験豊富なプレイヤーに協力してもらうことで、攻略のコツを実際に見て学べます。また、他のプレイヤーが残したメッセージ機能も非常に有用で、隠し通路の場所や敵への対処法など、貴重な情報を得られるでしょう。
ただし、協力プレイを使いすぎると自分の成長につながらない場合もあるため、適度に活用することが大切です。
Lies of Pはやりやすい死にゲー
Lies of Pは、2023年にリリースされた比較的新しい死にゲーで、従来の作品と比べて格段にやりやすい設計になっています。韓国のスタジオが開発した本作は、ピノキオの物語をダークファンタジー風にアレンジした独特な世界観が魅力的です。
死にゲー初心者にとって取っつきやすい要素が多く盛り込まれているため、「最初の死にゲー」として選ぶ人も増えているようです。
美麗なグラフィックで世界観に没入
Lies of Pの最大の魅力の一つが、美麗なグラフィックによる圧倒的な世界観の表現力です。ヨーロッパの古い街並みを思わせる精緻な背景や、機械と生物が融合したような独特なデザインの敵キャラクターは、見ているだけでも楽しめる品質に仕上がっています。
筆者がプレイした際も、美しい景色に見とれてしまい、死にゲー特有の緊張感を忘れてしまう瞬間が何度もありました。この「世界を探索したい」という動機は、困難な戦闘を乗り越える原動力になってくれるでしょう。
特に、雨に濡れた石畳の表現や、夕暮れ時の街の雰囲気は秀逸で、現行機種のスペックを活かした映像美を堪能できます。
フロム系では優しい難易度設定
Lies of Pは、いわゆるフロム系(フロム・ソフトウェア風)の死にゲーの中では、比較的優しい難易度設定となっています。敵の攻撃パターンが分かりやすく、回復アイテムも豊富に用意されているため、初心者でも諦めずに挑戦し続けられるでしょう。
例えば、ボス戦で負けても、直前から再開できるため時間のロスが少なく済みます。また、武器の強化システムも理解しやすく、どうすれば強くなれるかが明確に示されているのです。
ただし「優しい」とは言っても、しっかりとした歯ごたえはあるため、達成感を損なうことはありません。
現代的なUIで操作しやすい
Lies of Pでは、現代的なUI(ユーザーインターフェース)が採用されており、古い死にゲーにありがちな「分かりにくいメニュー」や「不親切な情報表示」がほとんどありません。
インベントリ(持ち物画面)の整理がしやすく、装備の比較も一目で分かるようになっているため、ゲームシステムの理解に時間を取られることなく、戦闘や探索に集中できるでしょう。
また、クエストの進行状況も分かりやすく表示されるため、「次に何をすればいいか分からない」という状況に陥りにくいのも初心者には嬉しいポイントです。
仁王2は日本人におすすめの死にゲー
仁王2は、戦国時代の日本を舞台にした死にゲーで、特に日本人におすすめしたい作品です。歴史上の人物や妖怪が数多く登場するため、海外製の死にゲーよりも親近感を持ってプレイできるでしょう。
コーエーテクモゲームスが開発した本作は、日本の美意識と死にゲーの緊張感を見事に融合させた傑作と言えます。
戦国時代が舞台で馴染みやすい
仁王2では、戦国時代という日本人にとって馴染み深い時代設定により、世界観に没入しやすくなっています。織田信長や明智光秀といった歴史上の著名な武将が登場するため、日本史に興味がある方なら特に楽しめるでしょう。
また、各地の名所や城郭も丁寧に再現されており、まるで歴史ドラマの中を冒険しているような気分を味わえます。筆者も本能寺の変を扱ったステージでは、歴史の重要な場面に立ち会っているような感動を覚えました。
海外製の死にゲーでは理解しにくい文化的背景も、日本が舞台なら直感的に理解できるはずです。
豊富なアクション要素で戦闘が楽しい
仁王2の戦闘システムは、豊富なアクション要素により非常に奥深く設計されています。武器ごとに「上段・中段・下段」の構えがあり、それぞれ異なる技を繰り出せるため、同じ武器でも多彩な戦い方が可能です。
さらに「妖怪技」という特殊な能力や、「守護霊」による支援など、他の死にゲーにはない独自のシステムが戦闘に深みを与えています。最初は複雑に感じるかもしれませんが、慣れてくると「こんな戦い方もできるのか」という発見が次々と現れるでしょう。
特に、残心(ざんしん)というタイミング良くボタンを押すシステムは、武道の精神性を表現した素晴らしいアイデアだと思います。
協力プレイで友達と攻略可能
仁王2では、最大3人での協力プレイが可能で、友達と一緒に困難なステージに挑戦できます。一人では心が折れそうになる場面でも、仲間がいれば乗り越えられることが多いでしょう。
筆者も友人と協力プレイを楽しんだ経験がありますが、役割分担をして戦略的に攻略していく過程は、ソロプレイとは全く違った面白さがありました。一人が敵の注意を引き付けている間に、他の人が背後から攻撃するといった連携プレイは爽快感抜群です。
ただし、協力プレイでは敵の体力も増加するため、必ずしも楽になるとは限らない点にご注意ください。
CODE VEINは簡単な死にゲー入門作品
CODE VEINは、死にゲーの中でも特に簡単な部類に入る入門作品として人気があります。バンダイナムコエンターテインメントが開発した本作は、アニメ風のキャラクターデザインと、初心者に配慮したシステム設計が特徴的です。
「死にゲーに挑戦してみたいけれど、あまりに難しいのは…」という方には、最初の選択肢として強くお勧めします。
NPCパートナーと常に2人で攻略
CODE VEINの最大の特徴は、NPCパートナーと常に2人でゲームを進められる点です。一人でのプレイに不安がある初心者にとって、この仕組みは非常に心強い味方となってくれるでしょう。
パートナーは単なるお飾りではなく、実際に戦闘で重要な役割を果たしてくれます。敵の注意を引き付けてくれたり、プレイヤーが倒れた時に蘇生してくれたりするため、一人では到底クリアできない場面も突破可能です。
筆者の経験では、パートナーのおかげで死にゲー特有の「一人で立ち向かう孤独感」がほとんど感じられませんでした。
アニメ調キャラクターで親しみやすい
CODE VEINでは、アニメ調キャラクターによって親しみやすい雰囲気が演出されています。従来の死にゲーにありがちな重厚で暗い世界観とは一線を画しており、特にアニメやゲームに慣れ親しんだ方なら抵抗なく入り込めるでしょう。
キャラクターメイキング機能も充実しており、自分好みの主人公を作り上げる楽しみもあります。見た目が気に入ったキャラクターなら、多少の困難があっても最後まで付き合いたくなるものです。
ただし、アニメ調とはいえ戦闘は本格的な死にゲーなので、油断は禁物でしょう。
ストーリー重視で楽しめる
CODE VEINは、ストーリー重視の作りになっており、キャラクター同士の関係性や世界観の謎を解き明かしていく過程が非常に魅力的です。単純に「強い敵を倒す」だけでなく、「この世界で何が起きているのか」を知りたいという動機でゲームを続けられます。
各キャラクターには詳細な背景設定があり、彼らとの交流を深めることで新たなストーリーが展開されるのです。筆者も気になるキャラクターの過去を知りたくて、多少難しい場面でも諦めずにプレイを続けられました。
死にゲーというと「ストーリーは二の次」というイメージを持たれがちですが、本作は物語性も十分に楽しめる作品と言えるでしょう。
Hollow Knightは2D死にゲーの名作
Hollow Knightは、2D横スクロール形式の死にゲーの名作として、世界中で高い評価を受けている作品です。オーストラリアの小規模な開発チームが作り上げた本作は、限られた予算の中で驚くほど高品質なゲーム体験を実現しています。
3D酔いが心配な方や、昔ながらの2Dアクションゲームが好きな方には特におすすめしたい一本です。
美しい手描きアートの世界観
Hollow Knightの最大の魅力は、美しい手描きアートによる幻想的な世界観にあります。すべてのグラフィックが手作業で描かれており、まるで絵本の中を冒険しているような美しさを味わえるでしょう。
地下世界の各エリアには、それぞれ異なる雰囲気と美しさがあります。緑豊かな森のエリアから、禍々しい深淵の底まで、多様な景色を楽しめるのです。筆者も美しい景色に魅了され、戦闘で負けても「もう一度この場所を見たい」という気持ちで再挑戦していました。
インディーゲームならではの芸術的なこだわりを存分に感じられる作品でしょう。
価格が安く手を出しやすい
Hollow Knightは、価格が安く設定されているため、初心者でも手を出しやすい作品です。通常のフルプライスゲームの半分以下の価格でありながら、50時間以上楽しめる大容量のコンテンツが用意されています。
「死にゲーに興味はあるけれど、高価なゲームを買って合わなかったらどうしよう」という不安がある方でも、この価格なら気軽に試せるのではないでしょうか。筆者も最初は軽い気持ちで購入しましたが、結果的に100時間以上プレイする大作となりました。
コストパフォーマンスを重視する方には、非常におすすめできる選択肢です。
メトロイドヴァニアとして独特の魅力
Hollow Knightは、メトロイドヴァニアと呼ばれるジャンルの要素を取り入れており、他の死にゲーとは異なる独特の魅力を持っています。新しい能力を手に入れることで、これまで行けなかった場所に行けるようになる探索の楽しさは格別です。
例えば、壁に張り付く能力を得れば、垂直の壁面を移動できるようになり、マップの見え方が一変します。この「能力獲得による世界の広がり」は、他のゲームジャンルでは味わえない特別な体験でしょう。
戦闘だけでなく、探索やパズル要素も楽しみたい方には最適の選択と言えます。
Salt and Sanctuaryは協力プレイ対応
Salt and Sanctuaryは、協力プレイ対応の2D死にゲーとして知名度を上げている作品です。アメリカの小規模スタジオが開発した本作は、「2D版ダークソウル」とも呼ばれるほど、本格的な死にゲー体験を提供してくれます。
特に、友達と一緒にゲームを楽しみたい方には強くお勧めしたい選択肢でしょう。
2D版ダークソウルとして人気
Salt and Sanctuaryは、2D版ダークソウルとして人気を集めており、3D酔いが心配な方でも安心して楽しめる死にゲーです。ダークソウルの核となる要素である「死んで学習する」「ソウルを集めて成長する」「高難易度だが理不尽ではない」といった特徴を、2D形式で見事に再現しています。
敵の配置やボス戦の設計も非常に巧妙で、3Dの死にゲーに引けを取らない緊張感とやりがいを味わえるでしょう。筆者も最初は「2Dで死にゲーの面白さが表現できるのか」と疑問に思っていましたが、プレイしてみると杞憂だったことがよく分かりました。
横スクロールアクションが好きな方なら、きっと気に入る作品のはずです。
友達と一緒に楽しめる仕様
Salt and Sanctuaryでは、友達と一緒に楽しめる仕様が搭載されており、一人では心が折れそうな難しい場面でも、協力して乗り越えられます。同じ画面で2人同時にプレイできるため、コミュニケーションを取りながら戦略を立てられるのです。
協力プレイでは、一人が前衛で敵と戦っている間に、もう一人が魔法で支援するといった役割分担も可能でしょう。筆者も友人とプレイした際は、お互いの得意分野を活かした連携プレイで、通常では困難なボス戦もクリアできました。
一人でプレイするのとは全く違った戦略性を楽しめます。
インディーゲームながら高品質
Salt and Sanctuaryは、インディーゲームでありながら高品質な作りになっており、大手メーカーの作品に劣らない完成度を誇ります。限られた予算と人員で作られたとは思えないほど、細部まで丁寧に作り込まれているのです。
特に、武器やアーマーの種類の豊富さ、スキルツリーの複雑さ、世界観の一貫性などは、大作RPGと比較しても遜色ありません。筆者も最初は「インディーゲームだし、そこまで期待しなくても…」と思っていましたが、実際にプレイしてみると期待を大きく上回る品質に驚かされました。
価格以上の価値を感じられる作品と言えるでしょう。
死にゲー初心者が知るべき攻略のコツと選び方
死にゲー初心者の皆さんが上達するためには、基本的な攻略のコツを理解し、自分に適した作品の選び方を知ることが重要です。ここでは、実際のプレイで役立つ具体的なテクニックと、失敗しないゲーム選びの方法をご紹介いたします。
初心者向け死にゲーの選び方のポイント
初心者向けの死にゲーを選ぶ際には、いくつかの重要な選び方のポイントがあります。闇雲に人気作品を選ぶのではなく、以下の基準に沿って検討することで、挫折せずに楽しめる作品に出会える可能性が高まるでしょう。
難易度調整機能があるかチェック
最も重要なポイントの一つが、難易度調整機能があるかチェックすることです。一部の死にゲーには、プレイヤーのスキルレベルに応じて難易度を変更できる機能が搭載されています。
例えば、「スター・ウォーズ ジェダイ:フォールン・オーダー」では、戦闘の難しさを4段階で調整可能です。最初は易しい設定でゲームの流れを覚え、慣れてきたら徐々に難易度を上げるという段階的なアプローチができるでしょう。
ただし、フロム・ソフトウェア製の作品のように、あえて難易度調整機能を設けていない作品もあります。これらの作品では、別の救済措置(協力プレイやレベル上げなど)が用意されていることが多いため、事前に確認しておくことが大切です。
協力プレイ対応かを確認する
協力プレイ対応かを確認することも、初心者には重要な選択基準となります。一人では突破できない難所でも、経験豊富なプレイヤーの協力があれば乗り越えられることが多いからです。
オンライン協力プレイに対応している作品なら、世界中のプレイヤーから支援を受けられます。また、ローカル協力プレイ対応なら、友人や家族と一緒に楽しめるでしょう。筆者の経験では、協力プレイ機能があるかないかで、初心者の挫折率は大きく変わると感じています。
ただし、協力プレイに頼りすぎると自分自身の成長につながらない場合もあるため、適度なバランスを保つことが重要です。
グラフィックや世界観の好み
グラフィックや世界観の好みも、ゲーム選びにおいて軽視できない要素です。どんなに優れたゲームシステムでも、世界観に魅力を感じなければ最後まで続けるのは困難でしょう。
ダークファンタジーが好きならエルデンリングやダークソウル3、戦国時代に興味があるなら仁王2、アニメ調のキャラクターが好みならCODE VEINといったように、自分の趣味嗜好に合った作品を選ぶことが継続の秘訣です。
筆者も「見た目が好みじゃない」という理由でプレイを諦めた作品がいくつかあります。逆に、世界観に惹かれた作品は多少難しくても最後までプレイできました。
プラットフォーム対応状況
最後に確認すべきは、プラットフォーム対応状況です。自分が持っているゲーム機やPCで動作するかを事前にチェックしておかないと、せっかく気に入った作品でもプレイできません。
特にPC版を選ぶ場合は、最低動作環境や推奨動作環境も確認しておきましょう。また、一部の作品ではPS5やXbox Series X/Sといった次世代機でしかプレイできない場合もあります。
購入前の確認を怠ると、後で困ることになりかねません。
初心者が覚えるべき基本的な攻略コツ
初心者が死にゲーで上達するために覚えるべき基本的な攻略コツをお教えします。これらのテクニックを身につけることで、格段に生存率が向上し、ゲームを楽しめるようになるでしょう。
1対1の状況を作ることが最優先
死にゲーにおいて最も重要なのは、1対1の状況を作ることが最優先だということです。複数の敵に同時に囲まれると、どんなに上手なプレイヤーでも苦戦を強いられてしまいます。
具体的な方法としては、弓矢や投擲アイテムを使って一体ずつ敵をおびき寄せたり、狭い通路を利用して敵の数的優位を無効化したりする戦術が効果的です。筆者も最初の頃は「強引に突っ込んで全部倒そう」と考えていましたが、この考え方を改めてから急速に上達できました。
我慢強く、確実に一体ずつ処理していく姿勢が重要でしょう。
まずは体力(HP)を30まで上げる
多くの初心者が見落としがちなのが、まずは体力(HP)を30まで上げることの重要性です。攻撃力を上げたくなる気持ちは分かりますが、生存することができなければ意味がありません。
体力が低いと、敵の攻撃を数回受けただけで死んでしまい、学習する機会すら得られないのです。しかし体力を十分に上げておけば、多少のミスをしても持ちこたえられるため、敵の攻撃パターンを観察する余裕が生まれます。
筆者の経験では、体力30は死にゲー初心者にとって一つの目安となる数値だと感じています。
装備重量を50%以下に抑える
見落とされがちな重要なポイントが、装備重量を50%以下に抑えることです。重い装備を身につけすぎると、回避動作が遅くなり、敵の攻撃を避けにくくなってしまいます。
多くの死にゲーでは、装備重量によってキャラクターの動きが変化する仕組みが採用されています。軽装備なら素早く動け、重装備なら防御力が高い代わりに動作が鈍重になるのです。初心者のうちは、防御力よりも機動力を重視することをお勧めします。
「守るより避ける」という発想の転換が、上達への近道となるでしょう。
死ぬことを恐れずトライ&エラー
最も大切な心構えは、死ぬことを恐れずトライ&エラーを繰り返すことです。死にゲーは文字通り「死んで学ぶ」ゲームなので、失敗を恐れていては上達できません。
一回の挑戦で完璧にクリアしようとするのではなく、「今回は敵の攻撃パターンを覚えよう」「次は新しい戦術を試してみよう」といったように、段階的に学習していく姿勢が重要です。筆者も最初は死ぬたびにイライラしていましたが、「これも学習の一部」と考えるようになってから、ゲームが格段に楽しくなりました。
失敗は成功への階段だと考えましょう。
やりやすい死にゲーの特徴
やりやすい死にゲーには、初心者が挫折しにくい共通の特徴があります。これらの要素を理解しておくことで、自分に適した作品を見つけやすくなるでしょう。
セーブポイントが多く配置されている
やりやすい死にゲーの特徴として、セーブポイントが多く配置されていることが挙げられます。死んだ時の巻き戻りが少なければ、失うものも少ないため、積極的に挑戦しやすくなります。
例えば、エルデンリングでは「祝福」と呼ばれるセーブポイントが非常に多く設置されており、ボス戦直前にも配置されています。これにより、何度負けても直前から再挑戦できるため、ストレスを感じにくいのです。
逆に、古い作品の中にはセーブポイントが少なく、一度死ぬと大きく戻されてしまうものもあります。初心者のうちは、なるべく親切な設計の作品を選ぶことをお勧めします。
レベルアップによる成長要素が豊富
レベルアップによる成長要素が豊富な作品は、初心者でも確実に上達を実感できるため、モチベーションを維持しやすいでしょう。プレイヤーのスキルだけでなく、キャラクターの能力向上でも困難を乗り越えられるからです。
仁王2やCODE VEINなどは、レベルアップによる恩恵が大きく、「昨日は勝てなかった敵に今日は勝てた」という成長を感じやすい作品です。この手応えがあることで、「もう少し頑張ってみよう」という気持ちになれるのです。
成長実感は継続の原動力となります。
チュートリアルが分かりやすい
初心者向けの死にゲーでは、チュートリアルが分かりやすく設計されています。基本操作や戦闘システムを丁寧に説明してくれるため、ゲームの仕組みを理解しやすいでしょう。
Lies of PやCODE VEINといった比較的新しい作品では、初心者への配慮が行き届いたチュートリアルが用意されています。一方、古い作品の中には「説明書を読んで理解してください」という設計のものもあるため、注意が必要です。
分からないまま進めても楽しめませんから、説明が充実した作品を選ぶことをお勧めします。
オンラインヘルプ機能がある
現代の死にゲーの多くは、オンラインヘルプ機能を搭載しており、他のプレイヤーからの情報を得られるようになっています。例えば、ダークソウルシリーズの「メッセージ機能」では、他のプレイヤーが残したヒントを確認できます。
「隠し通路がここにあるよ」「この敵は火が弱点だよ」といった情報は、初心者にとって非常に貴重でしょう。筆者も多くの場面で、先輩プレイヤーが残したメッセージに救われました。
一人で悩まず、コミュニティの知恵を活用することが上達の近道です。
初心者が避けるべき難しい死にゲー
初心者が最初に選んではいけない、避けるべき難しい死にゲーについても触れておきましょう。これらの作品は素晴らしいゲームですが、初回プレイには向いていません。
SEKIRO:パリィ必須で上級者向け
SEKIROは、パリィ必須で上級者向けの設計となっており、初心者には非常に厳しい作品です。敵の攻撃を正確なタイミングで弾き返す「弾き」システムの習得が必須で、これができないと全く先に進めません。
また、レベルアップによる救済措置がほとんどないため、純粋にプレイヤーのスキル向上が求められます。筆者も死にゲー経験を積んでからSEKIROに挑戦しましたが、それでも相当苦戦しました。
他の死にゲーで基礎を身につけてから挑戦することをお勧めします。
Bloodborne:攻撃的な立ち回りが必要
Bloodborneは、攻撃的な立ち回りが必要な作品で、初心者が慣れ親しんだ「守って反撃」という戦法が通用しません。盾がほとんど存在せず、常に攻撃し続けることが求められるからです。
さらに、世界観が非常に暗くグロテスクなため、ホラーが苦手な方にはお勧めできません。敵のデザインも気持ち悪いものが多く、見ているだけで不快になってしまう人もいるでしょう。
死にゲーに慣れてから、心の準備を整えて挑戦することをお勧めします。
古いタイトル:システムが不便
古いタイトルの多くは、現在の基準から見るとシステムが不便で、初心者には厳しい仕様となっています。ユーザーインターフェースが分かりにくかったり、セーブポイントが少なかったりする問題があるのです。
例えば、初代ダークソウルは名作ですが、移動速度が遅い、一部のエリアが理不尽、UIが不親切といった問題があります。これらは当時の技術的制約によるものですが、現在の快適なゲーム環境に慣れた人には辛く感じられるでしょう。
まずは現代的な作品で死にゲーの面白さを知ってから、古典に挑戦することをお勧めします。
死にゲー入門者向けの心構えと準備
死にゲー入門者が成功するために必要な心構えと準備について、最後にお話しします。技術的なコツも重要ですが、精神的な準備も同じくらい大切だからです。
死んで覚えるゲームと割り切る
何より重要なのは、死んで覚えるゲームと割り切ることです。死にゲーでは「死ぬこと=失敗」ではなく、「死ぬこと=学習」だと考える必要があります。
この発想転換ができると、死んでもイライラすることが少なくなり、「次はこうしてみよう」という前向きな気持ちでゲームを続けられるでしょう。筆者も最初はこの考え方に慣れるまで時間がかかりましたが、一度身につくと死にゲーの本当の面白さが分かるようになりました。
失敗を恐れず、学習を楽しむ姿勢が重要です。
攻略情報を積極的に活用する
初心者のうちは、攻略情報を積極的に活用することをお勧めします。「攻略サイトを見るのは邪道」と考える人もいますが、挫折してゲームをやめてしまうより、情報を参考にして楽しみ続ける方がずっと良いでしょう。
ただし、すべての情報に頼るのではなく、「どうしても分からない部分だけ」調べるという使い方がお勧めです。筆者も隠し通路の場所や、特定のボスの弱点など、限定的に攻略情報を参考にしていました。
情報は道具として上手に活用しましょう。
休憩を取りながらプレイする
死にゲーをプレイする際は、休憩を取りながらプレイすることが非常に重要です。集中力が切れた状態では判断力も鈍り、同じミスを繰り返してしまいがちだからです。
筆者の経験では、30分から1時間程度の休憩を挟むと、それまで倒せなかった敵に意外とあっさり勝てることがよくありました。一度頭をクリアにすることで、新しい戦略が思いつくこともあるのです。
無理をして続けるより、適度に休んだ方が効率的でしょう。
オンライン機能を有効活用する
最後に、オンライン機能を有効活用することをお勧めします。現代の死にゲーの多くには、他のプレイヤーと情報を共有したり、協力したりできる機能が搭載されています。
メッセージ機能、協力プレイ、プレイヤー同士の情報交換など、一人では解決できない問題も、コミュニティの力を借りれば解決できることが多いでしょう。筆者も多くの場面で、他のプレイヤーの助けに救われました。
死にゲーは決して「一人で黙々と挑戦するもの」ではありません。仲間と一緒に楽しむものなのです。
死にゲー初心者におすすめの作品選びまとめ
本記事でご紹介した内容を踏まえて、死にゲー初心者の皆さんが最適な作品を選び、楽しくプレイするための要点を以下にまとめます。
推奨作品について
- エルデンリング:オープンワールド設計と豊富な救済措置により、死にゲー初心者に最も適している
- ダークソウル3:シリーズ最高のバランスで死にゲーの基本を学べる王道入門作品
- Lies of P:美麗グラフィックと優しい難易度設定でやりやすさを重視した現代的作品
- 仁王2:戦国時代の世界観で日本人が馴染みやすく、豊富なアクション要素が魅力
- CODE VEIN:NPCパートナー同行とアニメ調デザインで最も簡単な死にゲー入門作品
- Hollow Knight:低価格で高品質な2D死にゲーの名作として手を出しやすい選択肢
- Salt and Sanctuary:協力プレイ対応で友達と一緒に楽しめるインディーゲームの傑作
選び方の基準について
- 難易度調整機能の有無:初心者は調整可能な作品を選ぶことで段階的にスキルアップ可能
- 協力プレイ対応:一人では困難な場面も他プレイヤーの支援で乗り越えられる
- 世界観とグラフィック:長時間プレイするため自分の好みに合った作品選びが継続の秘訣
- プラットフォーム対応:所有するゲーム機での動作確認は購入前の必須チェック項目
攻略の基本コツについて
- 1対1の戦闘状況作成:複数の敵との同時戦闘を避け、確実に一体ずつ処理する戦術が最重要
- 体力優先の成長方針:攻撃力より体力を30まで上げることで学習機会を確保できる
- 装備重量50%以下維持:機動力重視の装備選択により回避性能を最大化する
- トライ&エラーの積極採用:死を恐れず段階的学習を繰り返すことが上達への近道
やりやすい作品の特徴について
- セーブポイント多数配置:死亡時の巻き戻りが少なくストレスを軽減する親切設計
- 豊富な成長要素:レベルアップによる確実な能力向上でモチベーション維持が可能
- 分かりやすいチュートリアル:基本システムの丁寧な解説により理解しやすい導入部
- オンラインヘルプ機能:他プレイヤーからの情報共有で一人では解決困難な問題も解消
避けるべき作品について
- SEKIRO:パリィ必須のシステムとレベルアップ救済なしで上級者専用の高難易度
- Bloodborne:攻撃的立ち回り必須と暗いホラー世界観で初心者には精神的負担が大きい
- 古いタイトル:不便なシステムと理不尽な設計で現代基準では初心者に優しくない仕様
心構えと準備について
- 学習型ゲームとしての理解:死亡を失敗ではなく学習過程と捉える発想転換が必要
- 攻略情報の適度な活用:完全自力にこだわらず困った時のヒント程度に情報を参考にする
- 適切な休憩の挟み込み:集中力維持のため30分~1時間程度の休憩で判断力を回復させる
- オンライン機能の積極利用:コミュニティの知恵と協力を活用して一人では困難な壁を突破する

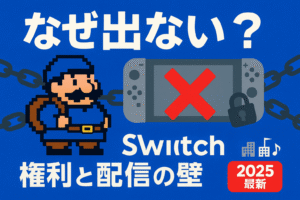


コメント