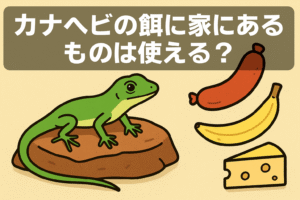カナヘビを飼育していると、「なんだか元気がない」「目を閉じたまま動かない」「脱皮がうまくいかない」など、体調不良のサインに気づくことがあります。
しかし、爬虫類の病気はわかりづらく、対応が遅れると命に関わることも珍しくありません。
この記事では、カナヘビの病気一覧と症状別の対応方法をわかりやすく解説します。
さらに、病気を防ぐための飼育環境の整え方や、初心者でも実践できる健康チェック法まで網羅。
「何をすればいいかわからない…」と不安を感じている方でも、この記事を読むことで毎日のケアが自信に変わるはずです。
あなたのカナヘビが元気で長生きするために、今すぐチェックしておきましょう。
カナヘビの病気一覧と症状別の対応方法
クル病(骨がやわらかくなる病気)
カナヘビの飼育で最も注意したい病気のひとつが「クル病」です。
この病気は、カルシウムやビタミンD3が不足したり、紫外線が足りなかったりすると起こります。
【主な症状】
- 背骨や足が曲がってくる
- 動きがゆっくりになる
- 口を開けたままになる
ある日、飼い主さんから「カナヘビの足が変な方向に曲がって動かない」と相談を受けたことがありました。詳しく話を聞くと、カルシウムを含んだ餌は与えておらず、日光浴もほとんどしていなかったとのこと。これは典型的なクル病のケースです。
【原因】
- カルシウムの不足
- ビタミンD3の不足
- 紫外線(UVB)の照射不足
【対応方法】
- カルシウム入りの粉を餌にまぶして与える
- 紫外線ライト(UVBライト)を使用する
- 屋外で安全に日光浴させる(直射日光が最も効果的)
【予防法】
- 昆虫などの餌にカルシウムパウダーをつけて与える
- 1日30分〜1時間程度の日光浴を習慣にする
- ビタミンD3入りのサプリを適切に使う
「カナヘビ 病気 一覧」の中でも特に重症化しやすいのがクル病です。早めの対応がカギになります。
脱皮不全(皮がうまくむけない)
カナヘビは定期的に脱皮を行いますが、環境が整っていないと皮がうまく剥けないことがあります。これを「脱皮不全」と呼びます。
【症状】
- 指先や尾の先に古い皮が残る
- 目の周りに白い膜のようなものが見える
- 脱皮中に動かずじっとしている
読者さんの中には「うちのカナヘビ、目が開かない」と心配される方もいましたが、実は脱皮不全による膜が原因でした。
【原因】
- 湿度不足(目安は60〜80%)
- 栄養が足りていない
- 体力が落ちている
【対応方法】
- 霧吹きで毎日水をかける(朝と夕方がおすすめ)
- 湯加減37℃ほどの温水で5分程度の温浴をさせる
- 手で剥がさず自然に脱げるように待つ
【予防法】
- 湿度計で環境をこまめにチェック
- ビタミンやミネラルが豊富な餌を使う
- 水分補給用の容器を常設する
目を閉じる・目が開かない

カナヘビが目を閉じたままなのは、体調不良のサインかもしれません。
【症状】
- 目をずっと閉じている
- 目が腫れている
- 目やにが出ている
特に、脱皮中に目を開けないままでいると心配になります。このときは無理に触らず、飼育環境を見直してみましょう。
【原因】
- 脱皮不全による膜の残り
- 結膜炎などの病気
- 紫外線不足や餌の偏り
【対応方法】
- 紫外線ライトを再点検(UVBの照射があるか確認)
- 湿度を60〜70%に保つ
- 異常が続く場合は爬虫類対応の動物病院へ相談
【予防法】
- 日光浴を習慣づける
- 目の周囲に汚れや皮が残らないようにチェックする
- 清潔なケージ環境を保つ
口内炎(マウスロット)
口内炎は、人間だけでなくカナヘビにも起こります。特に「マウスロット」と呼ばれる症状は深刻です。
【症状】
- 餌を食べない
- 口を開けっぱなしにする
- 口の中に白いかさぶたができている
ある飼い主さんは、カナヘビが餌をくわえてもすぐに落とすので異変に気づき、早めに病院に連れて行ったことで助かりました。
【原因】
- 餌の食べ方で口に傷がついた
- 水が汚れていて口の中に菌が入った
- 体力や免疫力の低下
【対応方法】
- ケージ内を清潔にする
- 飲み水を毎日交換する
- 初期であれば抗菌用のぬるま湯で口をゆすがせる(獣医指導下)
【予防法】
- 口を傷つけない柔らかめの餌を与える
- ストレスを減らし免疫を保つ
痛風(関節が腫れる)
カナヘビの関節が膨らんでいる場合、それは「痛風」かもしれません。
【症状】
- 足の関節がぷっくり腫れる
- 動きが遅くなる
- 餌を食べない
【原因】
- タンパク質が多すぎる餌(コオロギの与えすぎなど)
- 飲み水が少ない
- 腎臓の働きが弱っている
【対応方法】
- 餌の種類を見直す(昆虫を減らし、ミルワームなどを制限)
- 水入れを増やす・こまめに取り替える
- 定期的に体重や動きをチェック
【予防法】
- 週に1日は餌抜き(胃腸の休息日)を作る
- バランスよく餌をローテーションする
熱中症(日射病)
特に夏場に多く、気づくのが遅れると命に関わります。
【症状】
- ぐったりして動かない
- 口を開けて呼吸している
- 目を閉じたまま動かない
【原因】
- 高温・多湿の環境に長時間いる
- 直射日光を長時間浴び続けた
- ケージ内に風が通らない
【対応方法】
- すぐに涼しい場所に移動させる
- 水分を補給させる(口元に水滴をつける)
- 冷えすぎないようタオル越しに保冷剤を使用
【予防法】
- 温度管理は28〜30℃前後を目安に調整
- 直射日光が当たる時間は30分以内に
🔷 カナヘビの病気を防ぐ飼育環境と管理法
カナヘビを健康に育てるには、病気を未然に防ぐ飼育環境の整備が欠かせません。ここでは、初心者の方でもできる基本的な管理法をご紹介します。
🔹 栄養バランスの整った餌とは
病気を予防する第一歩は「餌の見直し」から始まります。実際、カルシウム不足が原因のクル病や、栄養偏りによる脱皮不全は、日々の食事で十分に防げるのです。
■ 餌の基本構成
- 主食:小さめのコオロギやミルワーム(※生き餌が基本)
- 補助:カルシウムパウダーをまぶす
- 週1〜2回:ビタミンD3を含むサプリメントを使用(過剰摂取に注意)
「カルシウムは入れているのに、なぜクル病になるの?」とよく聞かれます。実は、ビタミンD3が足りないと体がカルシウムを吸収できません。これは見落としがちな盲点です。
■ 餌の注意点
- 同じ種類の餌ばかりを与えない(栄養が偏ります)
- 餌の量は「頭の大きさの2倍」までが目安
- 残った餌はすぐ取り除き、ケージを清潔に保つこと
🔹 紫外線ライトと日光浴の重要性
カナヘビの健康には紫外線(特にUVB)が不可欠です。これは、カルシウムの吸収を助けるビタミンD3を体内で作るために必要なものです。
■ 室内飼育なら「紫外線ライト」は必須
- UVB対応の爬虫類用ライトを使う
- 毎日10~12時間、規則正しく照射
- ライトは6か月〜1年で交換(光は見えてもUVBが劣化します)
■ 屋外飼育なら「日光浴」を活用
- 曇りの日でも効果あり(UVBは雲を通過します)
- 直射日光で30分〜1時間が目安
- ガラス越しの日光では意味がありません(UVBが遮断されます)
一度、飼育者の方が「日光浴させているのにクル病になった」と相談に来ました。調べてみると、窓ガラス越しの光だったんです。これは実は多い間違いです。
🔹 湿度と温度管理の基本
カナヘビにとって適切な湿度と温度は、生きていくうえでの「空気と同じくらい」重要です。これを間違えると、脱皮不全や拒食、果ては命に関わる病気にもつながります。
■ 適正な飼育環境の目安
- 温度:日中25~30℃、夜間20℃前後
- 湿度:60~80%を目安に維持
- 季節に応じてヒーターや霧吹きを使い分ける
■ 温湿度管理に便利な道具
- デジタル温湿度計:一目で環境チェックができる
- パネルヒーター:夜間の温度低下対策に有効
- 霧吹き:脱皮期は特に朝晩2回が理想
🔹 清潔なケージ環境の保ち方
病原菌やカビの温床になりやすいのが「汚れたケージ」です。カナヘビの病気を防ぐには、清潔さの維持が何より重要です。
■ 掃除のポイント
- 毎日:フンや食べ残しはこまめに取り除く
- 週1回:床材の交換、止まり木や水入れを水洗い
- 月1回:ケージ全体を中性洗剤で洗浄・乾燥
■ おすすめの床材
- ペット用人工芝(清掃が簡単)
- キッチンペーパー(管理しやすく衛生的)
- ※細かい砂は誤飲リスクがあるため避けるのが無難です
あるベテラン飼育者は、「掃除こそ最大の健康法」と話していました。それくらい基本的で重要な作業です。
🔹 初心者でもできる健康チェック法
毎日の観察こそ、病気を早期発見する一番の近道です。初心者でもできるチェックポイントを覚えておきましょう。
■ チェックリスト
- 餌をきちんと食べているか
- 動きに元気があるか(登ったり、走ったり)
- 目や口に異常はないか(開いていない、濁っているなど)
- 排泄物は通常どおりか(色や硬さ)
■ こんな変化があったら要注意!
- じっとして動かない
- 口を開けたまま
- 足や背中が変に曲がっている
- 脱皮が途中で止まっている
毎朝カナヘビに「おはよう」と声をかけて様子を見ているだけでも、異変に気づけることがあります。それが命を守るきっかけになるかもしれません。
カナヘビの病気一覧に載るような症状は、日々の飼育環境でかなりの部分を防げます。今日からできることから取り組み、健康で元気なカナヘビライフを送りましょう。
✅ カナヘビの病気一覧から学ぶ予防と対策まとめ
カナヘビの病気を未然に防ぎ、健やかに育てるためのポイントを以下に整理しました。飼育初心者の方もベテランの方も、改めて基本を見直すきっかけにしてください。
- クル病:カルシウム・ビタミンD3不足と紫外線不足が主因。紫外線ライトと栄養補給で予防できる。
- 脱皮不全:湿度不足や体力低下が原因。霧吹きと温浴でサポート、清潔な環境も重要。
- 目を閉じる・開かない:結膜炎や脱皮不全による。湿度・栄養・紫外線の3点管理で改善が期待できる。
- 口内炎(マウスロット):不衛生な環境や免疫低下が原因。早期に獣医師に相談を。
- 痛風:高タンパク餌の与えすぎや水分不足に注意。餌の種類と水分補給のバランスがカギ。
- 熱中症(日射病):高温環境や直射日光の長時間照射で発症。温度・日光浴の時間管理が必要不可欠。
🔎 参考にしたカナヘビ飼育・病気に関する外部サイト
以下は、カナヘビの病気や飼育方法について信頼性の高い情報を提供しているサイトです。記事執筆にあたり、これらの情報をもとに内容を整理・再構成しています。
カナヘビ飼育のためのカナパパブログ
クル病・口内炎などの症状別解説が充実。初心者向けの飼育ノウハウも豊富。
とかげと暮らす「とかぼう」
脱皮不全、目の病気、熱中症への対応方法が詳しく掲載されています。
マイホームスタイル(カナヘビカテゴリ)
ケージ環境の整備や湿度管理など、実践的な飼育環境の構築方法に関する情報が豊富です。